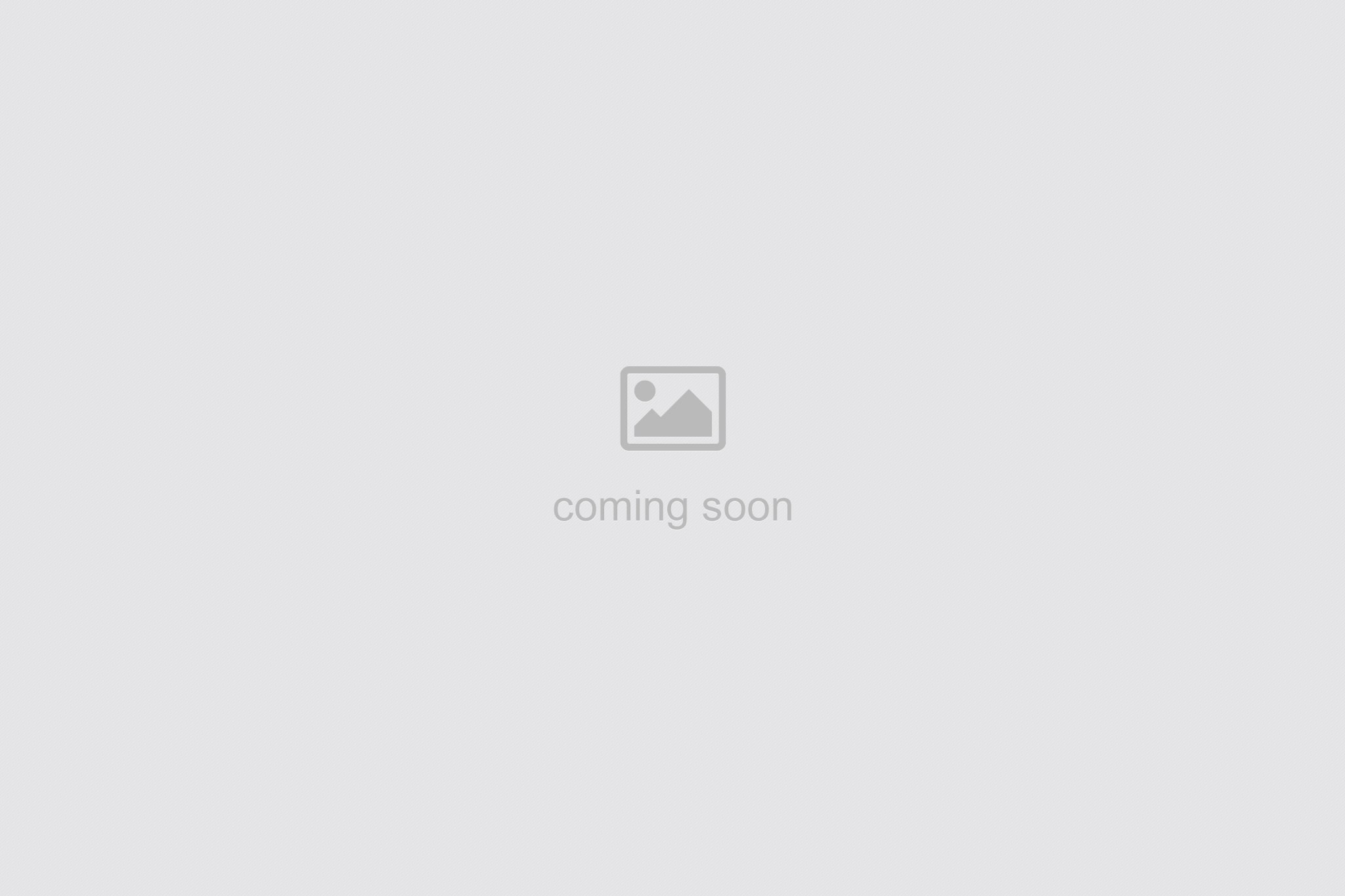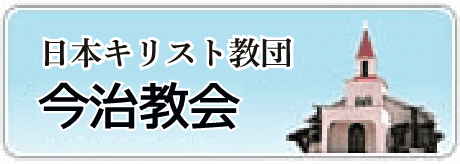園長だより
2024年度4月園だより
2023年度3月園だより
2023年度1月園だより
2023年度12月園だより
2023年度11月園だより
2023年度10月園だより
2023年度9月園だより
2023年度7月園だより
2023年度6月園だより
2023年度5月園だより
2023年度4月園だより
2022年度3月園だより
2022年度2月園だより
2022年度1月園だより
2022年度12月園だより
2022年度11月園だより
2022年度10月園だより
2022年度9月園だより
2022年度7月園だより
2022年度6月園だより
2022年度5月園だより
2022年度4月園だより
2021年度3月園だより
2021年度2月園だより
2021年度1月園だより
2021年度12月園だより
2021年度11月園だより
2021年度10月園だより
2021年度9月園だより
2021年度7月園だより
2021年度6月園だより
六月には花を飾って礼拝します。それぞれに子どもたちが持って来てくれた花を見ながら子どもたちに尋ねます。「王様やお姫様の服とこのお花とどっちがきれいかな?」
子どもたちはいつも「お花の方がきれい」と答えてくれます。よくわかっているなあと感心します。子どもたちは物事の本質、一番大切なことはしっかりとわかっていることがおおいです。
イエス・キリストも野原の花に目を止め、その花の美しさの中に神様の素晴らしい働きを直観したのです。そして神様はその花よりもずっとずっと私たちを愛してくださっていることを伝えました。花は、神様の素晴らしい御業を伝える共に神様の私たちへの愛の大きさを教えてくれています。このように愛されていることを喜び、その愛されている喜びを誰かと分かち合って、ますます豊かに喜びに満たされる。そんな喜びの分かち合いの経験を子どもたちと重ねていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
2021年度5月園だより
2021年度4月園だより
2020年度3月園だより
2020年度2月園だより
2020年度1月園だより
2020年度12月園だより
2020年度11月園だより
2020年度10月園だより
2020年度9月園だより
2020年度7月園だより
7月の聖句
2020年度6月園だより
2020年度5月園だより
2020年度4月園だより
2019年度3月園だより
2019年度2月園だより
2019年度1月園だより
2019年度12月園だより
2019年度11月園だより
2019年度10月園だより
2019年度9月園だより
2019年度7月園だより
2019年度6月園だより
2019年度5月園だより
2019年度4月園だより
2018年度3月園だより
2018年度2月園だより
2017年度1月園だより
2018年度12月園だより
2018年度11月園だより
2018年度10月園だより
2018年度9月園だより
2018年度7月園だより
2018年度6月園だより
イエス・キリストは、野の花には、神の愛の装いを、空の鳥には神の愛の養いがあると教えました。そしてなによりも私たち人間は、それらよりもはるかに神から愛されていると教えています。
六月、こどもたちはそれぞれに幼稚園の生活にも慣れ、周りに関心が向かい始めました。自然の美しさを子どもたちに伝え、そこに込められた神様の愛を、私たちへの愛をともに喜びつつ過ごしていきたいと思います。愛されている喜びこそ、子供達の生きる喜びと成長の最高の原動力であると信じます。今月もどうぞよろしくお願いします。
6月の聖句
「空の鳥を見なさい。あなたがたの天の父は鳥を養ってくださる」
マタイによる福音書第6章26節
2018年5月園だより
桜が咲いて、この前始園日、入園式だと思っていましたら、あっという間に桜も散り、新緑がまぶしい5月になります。今年は、泣く子が少ないように思えましたが、徐々に幼稚園に慣れ、緊張が解けてきたのか、最近になって泣く子が増えてきました。そういう過程を経て、本格的に幼稚園に慣れて行くのでしょう。これからが楽しみです。
さて、先日、教師会で教師に自分の名前の由来を尋ねてみました。それぞれの名前に親御さんの熱い願いが込められていることを実感し、とても感動しました。ご家庭の皆様も、子どもさんの名前をつける際には、一生懸命考え、思いを込め、願いを込めて付けられたことでしょう。
それぞれの名前は、それぞれ一人一人がかけがえのない尊い存在であること、愛された存在であることを伝えてくれています。名前って尊いものです。私も早く園児の名前を覚えないと・・・・
さて、聖書にはこう書いてあります。。
「門番は羊飼いには門を開き、羊はその声を聞き分ける。羊飼いは自分の羊の名を呼んで連れ出す。ヨハネによる福音書/ 10章 3節」
羊飼いは神様であり、イエス様です。羊は私たち人間です。神様は、私たち一人一人をかけがえのない尊い存在として大切に愛してくださいます。神様は私たち一人一人の名前をご存知なのです。「名前を呼ぶ」ことは、一人一人が愛され、尊ばれた命であることを確認する営みです。そしてその一人一人を神様は守り、導いてくださる羊飼いとなってくださいます。
幼稚園の保育が始まりました。私たち保育者は、子どもたち一人一人を大切な存在として尊び、愛する。その始まりとして名前を呼ぶことを大切にし、神様の愛と導きを伝える歩みに励みたいと思います。
5月もどうぞよろしくお願いします。
5月の聖句
『わたしは良い羊飼いである。』(ヨハネによる福音書/ 10章 11節)
2018年度4月園だより
3月園だより
2月の園だより
1月園だより
12月園だより
2017年11月園だより
先日の運動会は、延期になったにもかかわらず、たくさんお集まりいただき、温かい拍手、ご声援、ありがとうございました。
幼稚園の保育は運動会を経て、子供達はますます自信を深め、遊びが充実してきました。お友達と一緒にいることが楽しい、先生と一緒にいることが楽しい時期になりました。神様は、人間を、もともと誰かと共に生きる者として造られました。そしてその「共に生きる生き方」を祝福されました。今、その祝福された共に生きる歩みが充実してきています。
11月の聖書の言葉は
「二人または三人がわたしの名によって集まるところには、わたしもその中にいるのである。」マタイによる福音書第18章20節
この言葉は、「一人ではダメなの?」という疑問を持たれることがあります。「一人だったら神様は一緒にいてくださらないの?」という疑問です。そんなことはありません。神様は一人でも一緒にいてくださいます。この言葉は、神様は、人と人とが共に生きるようにしてくださり、その共に生きる歩みを祝福してくださることを伝えています。私たちは、そのこども達と共に生きる形をより豊かな祝福溢れるものとするために保育に励んでまいります。いよいよ実りの秋の集大成の十一月、とても楽しみです。どうぞ宜しくお願いします。
2017年10月園だより
さて、人生はよく旅にたとえられます。幼稚園生活は、こどもたちにとって、家庭生活から集団生活への新しい旅立ちということができるでしょう。そしてそれは人生の最初の旅立なのでしょう。
皆様の大切なこどもさんを幼稚園にお受け入れするということは、幼稚園生活という新しい旅に、こどもさんとご家族をお招きしたということです。そしてこの「旅」のもたらす素晴らしい成長と喜びをお約束をしているということです。こどもたちも、ご家庭の皆さまもこの約束を信じて、この幼稚園での生活、「旅」を始められたということができると思います。
この「旅」は決して一人ぼっちの旅ではありません。私たち教師は、ご家庭の皆さまとご一緒に、こどもたちの「旅」に寄り添い、こどもたちの生きる喜び、成長の喜びという「旅」の充実のために日々の保育に励んでおります。
10月の聖書の言葉は
「アブラムは、主の言葉に従って旅立った」創世記第12章4節
アブラム(アブラハム)は70歳の時に神様から新しい旅を始めなさいと言う言葉を聞きました。70才で新しい旅をしなさいというのは、ずいぶんと無茶な話です。でもアブラハムは神様の祝福の約束を信じて旅立ちました。神様はアブラムとの約束を守り、アブラムの旅に寄り添い、助け、導き、素晴らしい旅の実りを与えてくださいました。
私たちもアブラハムの信頼に応えて下さった神様に習い、子供達とご家庭の皆さまの信頼に応え、素晴らしい旅の実りを実現してまいりたいと思います。10月もよろしくお願いいたします。
2017年9月園だより
皆さま、ご無事でしたでしょうか?事故にあわないように、病気(特に熱中症)にならないように、再会を楽しみしつつお祈りしておりました。
実は私、ディズニーが大好きです。絵も素敵ですが、音楽が素晴らしい。最近では「アナと雪の女王」の「ありのままで」が大ヒットしました。私が特に好きな曲は「星に願いを」です。映画の始まりでコオロギが夜空の星に向かって歌います。願い続けたらかなら叶う。とても暖かく夢のある歌です。
こどもたちは様々な願いを持っていることでしょう。「大きくなったら・・・になりたい」とか「・・・ができるようになりたい」とか「・・・が欲しい」とか。「・・・が欲しい」というと大人だといささか嫌味に聞こえることもありますが、こどもたちの願いはとてもストレートで嫌みがありません。
こどもたちは前向きです。常に未来に向かって、伸びていこうとしています。いろんな願いを持ちます。私たち大人はこどもの願いを聞いて、「そうだね」「できるといいね」、「かならずできるよ」、「かならずなれるよ」こどもの心に寄り添い、夢を、願いを応援したいものです。
もちろん全ての願いが叶うものでもありません。中には「ちょっとどうなの」ということもないわけではありません。でも、あきらめずに願い続けていたら、願いがかなうように一生懸命努力していたら、素晴らしい未来が待っている。その希望をこどもたちと一緒に大切に育てていきたいものです。
「求めなさい。そうすれば、与えられる」マタイによる福音書第7章7節
9月の聖書の言葉です。
秋、こどもたちの前向きな気持ち、夢に寄り添いながら、実りの秋の喜びを分かち合えるように精一杯努めてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。
毎週、金曜日は幼稚園の礼拝です。賛美歌を歌い、お祈りし、聖書のお話を聞きます。ひよこ組さんからほし組さんまでみんなとても立派にお話を聞くことができます。昨年、初めて礼拝した時、子どもたちが良いお話によって育てられているなあと思いました。先生方が良いお話をなさっていたから、子どもたちはお話が大好きで喜んで聞いてくれるのでしょう。
さて、先日、研修会で「命は与えられたものである」と習いました。確かに命は「いただきもの」です。私たちがいただいている最高の「贈り物」、「プレゼント」です。前任の幼稚園で子どもたちに「プレゼントをもらったらどうする?」と尋ねますと、こどもたちは、「ありがとうと言う」と答えてくれました。「もらったプレゼントはどうするのかな?」と更に尋ねましたら、「大事にする」という答えてくれました。私たちは自分の命が与えられていることに感謝し、大切にしなければなりません。もちろん他人の命も同様に大切にしなければなりません。このことは幼児期にしっかり伝えたい人生の知恵の根本です。
実は命ばかりではなく、この世界も神様からの「贈り物」です。神様は愛を込めて、心込めてこの世界を造られました。自然、そして全ての命を造られ、この世界を祝福されました。そしてこの世界を私たち命あるものすべてに贈り物としてくださったのです。世界は、神様の愛の贈り物です。この世界で、神様の愛をいただき、生きる喜びにあふれてみんなで神様に感謝し、この世界を大切にするのです。この世界は、そんな神様への感謝を表す「ステージ」なのです。
特に自然の中で、共に遊び、共に過ごす時、私たちは神様の愛を共に喜び、感謝することができます。これから夏、神様の造ってくださった世界に生きる喜びを遊びの中で子どもたちが存分に感じ、感謝し、喜びに輝いて過ごしてくれるように励んでまいります。
残り少ない一学期となりましたが、どうぞ宜しくお願いします。
『7月の聖句』 天よ、喜び祝え、地よ、喜び踊れ。(詩編96編 11節)
私たちは、子どもと出会うことで、子どもからたくさんの幸せをいただきます。子育て、教育は楽なことばかりではありませんが、子どもから頂く幸せは何にもまさる喜びです。
少し前、今年度初めてほし組の子供達と給食をいただきました。その翌日、園庭に出てみましたら、ほし組の子どもたち何人かが集まって来て、ニコニコしながら「園長先生、今日の給食、どうするん?」と声をかけてくれました。その心は「園長先生、昨日一緒に給食食べて楽しかった。今日も一緒に給食食べよう。でした。残念ながらその日は別の予定が入っていたのですが、とてもとても嬉しかったです。関西弁で言えば、自分に向かって「おまえ、どんだけ幸せやねん」となります。本当に子どもたちは、私たちに幸せを与えてくれます。そういえば、自分の子どものことを振り返っても、子どもが生まれてくれて、たくさんの幸せをもらったことが思い出されました。
さて、私たちの幼稚園では「キリスト教保育」という雑誌の「聖書にきく」というコラムを参考にして聖書を学んでいます。毎年、執筆者が変わります。以前は、当幼稚園の元園長榎本栄次先生も書いておられました。今年度の執筆者は、石川県の先生です。私は前任地がお隣の福井県でしたから、この先生はとてもよく存じています。私が心から尊敬する方です。「やるべきことをやる。愛にあふれた方」です。私の前任の教会の信徒さんが、石川県におられた頃、生まれた子どもさんに重い病気があったのです。その時、この先生が慰め、励ましてくださいました。それを聞いてから、私はずっとこの先生を尊敬しています。またお話や執筆を通して、沢山のことを学ばせていただきました。「目から鱗」の経験をたくさんさせてくださいました。
今回の目から鱗は「奇跡」ということについてでした。普通「奇跡」といえば、通常では起こり得ない出来事を指して「奇跡」と呼びます。ところが、この先生は、「奇跡は神のなさることである」と言われたのです。これは本当に「目から鱗」でした。私たちの日常のなんの変哲もない出来事の中でも「神様がなされた」と思えることがあれば、それが「奇跡」なのだというのです。子育てにおける子どもの成長の姿。そこにはご家庭の皆様、教師の関わり、努力によるところも大きいでしょう。でもそれだけでは言い尽くせない不思議があるのではないでしょうか?自分も子育てに努めた。でもそれだけで子どもがここまで成長したとは思えない。そんな「プラスα」がありはしないでしょうか?自分の子育てを振り返ってみてもそうです。もちろん親として妻と共に一生懸命に努めました。でもそれだけで子どもが育ったとはどうしても思えません。沢山の方に支えられた。そして何よりも神様に守っていただいたとしか思えないのです。そもそも子どもを与えられるということ自体が、人の力だけではどうしようもない「奇跡」です。子どもは「作る」のではありません。与えられるのです。授かるのです。それは神様のなさること、奇跡ではないでしょうか?そう思って、幼稚園の子ども達の様子を見ていますと本当に日々、成長していきます。もちろんそこには保護者の皆様、教師の努力もありますが、神様が子どもたちを愛してくださって、素晴らしい祝福を与え、成長させてくださっているという「奇跡」が満ち満ちているように思え、感謝と喜びが溢れてきます。そしてますます保育に一生懸命に励もうという意欲を新たにさせられます。
今月の聖書の言葉は
「これは主の御業、私たちの目には驚くべきこと」詩編118編23節
日々成長していく子どもたち、神様のなされる素晴らしい「奇跡」を驚き、喜び、励まされながら、今月も保育してまいります。どうぞよろしくお願いします。
幼稚園が始まりました。泣く子が少ないようで、外遊びも始まり、幼稚園は順調なスタートを切ることができました。
ところで、先日、礼拝後のことです。ある女の子がやってきてある子から
「園長先生、小公子好きなんやろ 私も読んどる」と言われました。すごい。この子、親御さんから私が園のお便りに書いた巻頭言を読んでもらったのでしょう。とてもとても嬉しかったです。
さて、時々こういう質問をいただきます。「おたくの幼稚園はキリスト教の幼稚園らしいが、信者の子どもしか入れないのですか?」
私は「いいえ。そんなことはありません。私たちの幼稚園の根本にあるキリスト教の精神を理解してくださる方なら宗教に関係なく、お受け入れしています。」とお答えしています。キリスト教の精神とは「人間を超えた大いなる存在である神に守られ、愛されていることを喜び、神を敬って、神に喜ばれるように生きる」ことです。神は目に見えません。でも確かにおられて、自分たちを守っていてくださる。そのように目に見えない神を敬い、その方に喜ばれる者として生きる。悲しまれることはしない。それがキリスト教教育、宗教教育の大切なポイントです。
そのようにして、目に見えない神を敬うことは、目に見えないものを大切にすることへとつながります。大人の世界は目に見える結果を求めます。子ども達もいずれはそういう社会に出ていかなければなりません。でも目に見えるもの 目に見えないもの、本当はどちらが大切でしょうか?
たとえば、贈り物。贈り物は目に見えます。でも贈り物に込められた心は目に見えません。贈り物は、物ですから、いつか古びていきます。でも贈り物に込められた愛情は、古びることはありません。昔、父から時計をもらいました。もう動きません。でもその時計に込められた父の愛は決して古びません。その時「大事にしてください」との父の言葉、父の眼差しも私の心に焼き付いています。贈り物を本当に喜ばしい「贈り物」にしてくれるのは、愛だったり、感謝だったり、思いやりだったり、贈る人の心です。
サン・テクジュベリの「星の王子さま」で狐が王子に言います。「本当に大切な者は目に見えないんだよ。」。目に見えるものは、目に見えないものによって支えられています。目に見えるものを意味あるものとするのは、目に見えない心です。愛 思いやり 感謝 大切な心は目に見えません。でも、それがあって、愛、感謝、思いやりが目に見える行動として現れてくるのです。
私たちは幼稚園において、常に目に見えないものを大切にしています。目に見えるものがどうでも良いのではありません。作品一つにしても、結果としての作品よりもそれに至るまで子どもたちがどれだけ感動したか、楽しんだか、どんな思いを込めて作ったのか。そういう目に見えないものとのつながりの中で目に見えるものを理解し、意味づけていきます。
五月の聖書の言葉は、 「わたしたちは見えるものではなく、見えないものに目を注ぎます。」です。私たちの保育において、一番伝えたい大切なものも、目に見えません。それは神様の愛です。イエス・キリストにおいて、子どもたちを愛し抜かれる神様の愛を幼稚園の活動、施設設備、なによりも教師の働きかけを通して伝えます。そして子どもたちに愛される喜び、生きる喜び、生きる力、感謝と思いやりの心を育んでいきます。これも目に見えません。でも、それら目に見えないものをしっかりと大切に育てていく営みが、いずれは目に見えるものへと繋がっていきます。生み出していきます。
5月もどうぞよろしくお願いします。
四月、新入園、進級、新しい生活が始まりました。
期待と共に不安もあることでしょう。新入園児にとっては、家庭から離れて集団生活に入ります。初めての経験でしょう。進級するこども達も一つ大きくなった喜びと共に新しい生活には不安もあることでしょう。
そんな四月、新しい生活の始まりの時、私たちはすべてのこども達がそのありのままの姿で受け入れられ、歓迎されていることを実感してもらうことから保育を始めます。まずは教師の笑顔、やさしい言葉かけから始めます。「よく来てくれたね。ありがとう。うれしいよ。大好きだよ。安心して、一緒に遊ぼうね。」そんなメッセージを幼稚園の保育全体でこども達に伝えます。
四月の聖書の言葉は「あなたがたに平和があるように」(ヨハネによる福音書第20章19節)です。
この言葉はイエス・キリストの復活の物語の中に出てきます。イエス・キリストは十字架にかけられて三日後に復活されました。そして弟子達に出会われました。弟子達の心は真っ暗でした。イエス・キリストが捕らえられる時に、逃げてしまい、イエスを守ることも、イエスについていくこともできませんでした。大きな挫折感、自己嫌悪、悲しみ、不安で弟子達の心は冷え切り、固く閉ざされていました。そんな弟子達に対して、復活されたイエス・キリストは「あなたがたに平和があるように」と呼びかけたのです。「安心しなさい。わたしだよ」という意味です。もっと言えば、「安心しなさい。わたしは今もあなたがたのありのままを愛しているよ。」というメッセージです。このイエス・キリストの愛の挨拶によって、弟子達は安心し、固く閉ざされた心は開かれていったのでした。
この弟子達ほど、深刻ではないでしょうが、この時期のこども達の心の不安は弟子たちと似ているところがあるように思います。新しい生活への不安です。そのようなこども達に対しても、イエス・キリストは「あなたがたに平和があるように」、「安心しなさい。あなたのありのままが大好きだよ。」と呼びかけておられます。このイエス・キリストの心にならって、わたしたちもこども達のありのままを受け入れ、安心して幼稚園生活を始めることができるように努めてまいります。
こどもたちばかりではなく、ご家族の皆様も不安やご心配があるかもしれません。そのような折にはどうぞいつでもお声をお掛け下さい。
そのようにして、四月、安心して「であう」月としたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
四月になりました。私が今治の地にまいりまして一年が過ぎました。四国の第一印象は桜がとても綺麗でした。今年も楽しみです。でも何よりも楽しみなことは、こどもたちと共に新しい年度の歩みを始めることです。
さて、私たちの今治めぐみ幼稚園はキリスト教保育の幼稚園です。保育の根本にキリスト教精神を置いて、そこを出発点として保育を行います。聖書の言葉を大切にし、年間聖句、毎月の聖書の言葉に学びながら保育を行っています。日々こども達と分かち合っています。
今年度の年間聖句は
「あなたがたは神に愛されている子供です。」 エフェソの信徒への手紙5章1節
です。
すべての人は、神様から愛されている尊いかけがえのない存在です。その愛されている喜びを実感して、その愛に応えて互いに愛し合う者として歩む。それがこの聖書の言葉のメッセージです。そしてこの聖書の言葉のメッセージを幼稚園の生活を通して、こども達に伝えていきたいと思います。神様から愛され、家族から、教師から愛され、喜び、その愛に応えて、愛する者として歩むことを目指します。
私がこどもの頃大好きだった本の一つが「小公子」です。その中で忘れられない一節があります。「父親は母親にやさしい言葉で話しかけた。すると生まれたこどももやさしい言葉で母親に話すようになった」。
何もないところからは何も生まれません。ない袖は振れません。人は受けたことを出していくのです。幼い日に愛されて、やさしい言葉をたくさんもらったら、やさしい心に育てられて、やさしい言葉をたくさん話すようになるのです。たくさん愛をいただいて、愛される喜びに輝いて、愛する者として歩んでいってほしい。そう願っています。
その愛の根本にすべての人を愛する神様の愛があります。今の日本社会、そのような愛が見失われているとしか思えないような出来事がたくさん起きています。心が痛みます。だからこそ、私たちはすべての人が愛されている。すべてのこども達が愛されているその喜びを実感していただける保育をこの年も行ってまいります。
皆様のご理解とご協力をよろしくお願いします。
室内行事ではありますが、天気が気になりました。私が会場に歩いて到着した午前9時ごろは曇り。ああよかった。発表会が終わって、歩いて幼稚園に着いたその時も雨はなし。でも発表会の間はザアザアと雨が降っていたとのこと・・・・
そんな発表会。主催者の私が申し上げるのはおかしいかもしれませんが、こどもたちの成長の輝き、生きる喜びの輝きに圧倒されてしまいました。それから子どもたちと教師の心の結びつき、さらに子どもたちを温かく見守るご家族の眼差し、一番大好きな人たちに見てもらえる、拍手してもらえる喜びが満ち溢れていて、結局、私の目はやっぱり「雨」でした。目だけで済んだらよかったのですが・・・
誤解を恐れず申します。私は発表会当日の「結果」よりも当日に至るまでの歩み、「過程」の方が大切だと考えています。この発表会で子どもたちとともに何を実現したいのか、どんな成長を願うのか、そのために当日に向けて、どう歩んでいくのか?当日に向けてどれくらい楽しめたか、どれくらい成長できたか?どれくらい生きる喜びを感じていたか?さらにそれがこども同士で、また教師とこどもで、励ましあい、支え合って歩んでくることができたか。そのような過程が当日の結果へとつながっていきます。そのような過程こそが子どもたちにとって最も大切だなのです。
そのようにして培った幸せな経験が子どもたちの人間性の深いところに根付いて、子どもたちの一生の基礎となっていくことでしょう。
主はわたしの光、わたしの救い わたしは誰を恐れよう。
主はわたしの命の砦 わたしは誰の前におののくことがあろう。詩編27編1節
子ども達のこれからの歩みも神様が光を照らして導いてくださる。そんなおおらかな人生への信頼をもってそれぞれに新しい歩みへと踏み出して欲しいと思います。
「一月は急ぐ、二月は逃げる、三月は去る」。とうとう三月です。でも、子どもたちの時間はまだまだあります。最後まで、子ども達の幸せと成長のために精一杯努めてまいります。どうぞよろしくお願いします。
一年で一番寒い時期を過ごしています。皆様いかがお過ごしでしょうか?幼稚園では少しずつインフルエンザによるお休みが出てきて心配しています。
私は、福井県の敦賀市からまいりました。その前は岩手県におりました。そういう身からしますと今年は随分暖かい冬を過ごさせていただいています。朝夕は少し冷え込むようですが、日中お天気が良いと暖かくて、ひよこ組のこども達は、園庭の人工芝の上で裸足で遊んでいました。ちょっとびっくり。まさしく「温暖」な地域なのですね。
こども達は若干お休みの子もいますが、元気に登園してきています。休みが明けて、スムーズ三学期の生活に入っていけたようです。残り少ない三学期、良いスタートを切ることができたようでホッとしています。
さて、2月の聖書の言葉は、
「わたしたちは見えるものではなく、見えないものに目を注ぎます。」(コリントの信徒への手紙二第4章18節)です。
目に見える結果が求められる世の中です。でも目に見えるものは目に見えないものに支えられていることを忘れてはいけません。「目に見えないもの」とは、何でしょうか?いろいろありますが、まず第一には「心」と言えるしょう。こども達の保育に当たる時、目に見える姿だけではなく、こども達の心の動きを常に大切にしていかなければなりません。今、こども達は何を感じているか、何を喜んでいるか、何に困っているか、何に興味があるのか、常にこども達の心を大切に、寄り添って保育してくことが大切です。「目に見えないもの」として、次に手がかりになるのは「過程」です。もうすぐ生活発表も行われます。そこでの本番当日の目に見える結果も大切ですが、特に幼児期はその日に至るまでの過程、こども達がどれだけ楽しんだか、どれだけ努力したか、どれだけ成長したかを大切にして行きたいと思います。そしてそのように当日は見えない過程を大切にしていく中で、こども達に豊かな成長の喜び、生きる喜び、生きる力というもっと深い意味での「目に見えない」大切なものが育っていくことでしょう。
一月は行く、二月は逃げる、三月は去ると申しました。でも目に見えない子供達の心に寄り添い、一時日時を大切に歩む時、短く、早く流れていく時間にあっても素晴らし三学期となることでしょう。
今月もどうぞ宜しくお願いします。
寒中ですが、皆様のご健康をお祈りいたします。
旧年中はありがとうございました。本年もどうぞ宜しくお願いします。
皆様、それぞれに楽しいお正月を過ごされたことと思います。冬休みが明け、新しい年、こどもたちと再会できて、とても嬉しく思います。
遅まきながら、12月には今治めぐみ幼稚園でも初めてのクリスマスを皆様とご一緒できて本当に感謝でした。イルミネーション点灯式には「びっくり本(もう古い?)」。度肝を抜かれて始まり、アドヴェントクランツにロウソクの明かりを一つまた一つと灯しながら、礼拝を重ねて準備し、クリスマス当日を迎えることができました。聖誕劇(ページェント)では、こども達一人一人が、クリスマス物語の登場人物そのものに見えてきて、深い感動を覚えました。クリスマス物語そのものが持っている力を感じました。。こども達も劇に参加し、演じることで、クリスマス物語をより深く、より豊かに味わい、楽しみ、経験し、神様の愛を心の深いところに受け止めたことでしょう。またご家庭の皆様の温かい眼差し。こどもたちが一番観て欲しいのは、大好きなご家族です。そのご家族に愛情のこもった眼差しで観ていただき、心温まる幸せなクリスマスとなったことだと思います。幼稚園の営みがそんなご家族の幸せな思い出とこどもたちの豊かな成長のためにお役に立てたのであれば幸いです。私はと言いますと皆様の歌の指揮をさせていただくということで、とても緊張しました。歌は好きですが、指揮は苦手で果たしてお役に立てたものか?それはともかく、こどもたちは、クリスマスという夜の物語に光り輝く姿で明かりを灯してくれました。
さて、1月の聖書の言葉は、「光の子として歩みなさい。」(エフェソの信徒への手紙第5章8節)です。実はこの言葉、前任の幼稚園では毎年三月の聖書の言葉、卒園式に暗唱する言葉としておりました。そして私が下手な字で卒園生に送る聖書にこの言葉を書かせていただいていたのでした。個人的にも大好きですし、キリスト教保育の大切な要点を示してくれている言葉です。
「光の子」とは、愛されている喜び、成長する喜びに輝くこどものことです。その実現のために必要なことは、たくさんたくさん愛されることです。ご家族から、教師から、お友達から豊かな愛を受け、愛される喜びに輝いて、互いに愛し合う経験を重ねることです。その愛をいただき、その愛を反映して、こども達は光り輝くのです。光の源は、自分の内にあるのではなく、他から受けるのです。また、より根本的には、イエス・キリストに示された神様が、こども達を豊かに愛してくださっている、その神様の愛を幼児教育を通してこども達に伝えることがキリスト教主義幼稚園のつとめです。この聖書の言葉から、そのことの大切さを改めて思わされました。
さあ、三学期。年度末、保育の総仕上げの時期です。「一月は急ぐ、二月は逃げる、三月は去る」とも申します。焦ることなく、今を大切に、こども達と共に歩むことができる日々に感謝し、こども達が愛される喜び、成長する喜びに光り輝けるように精一杯保育に励んで参りたいと思います。どうぞ宜しくお願い致します。
皆様の新しい年に神様の祝福を心よりお祈りいたします。
園児「うん。そうだよ。」
私「やったー、だんだん覚えてきたでしょ」
園児「じゃあ、僕のお母さんのお名前知ってる?」
私「うーん。知らないなあ」
園児「じゃあ、教えてあげる僕のお母さんの名前はねえ〇〇っていうんだよ。」
私「そうか、そうなんだあ」
給食の時間、一生懸命子どもたちの名前を覚えています。こども達に名前を聞いたら、家族の名前まで教えてくれました。なんて幸せな子どもたちなんでしょう。名前を教えてもらった私は、それこそ「おすそわけ」をしてもらって、とても幸せな時間になりました。ご家族の愛のぬくもりに包まれているのだなと改めて思わされました。
クリスマスがやってきます。寒いけれども暖かい、なんだか嬉しいクリスマスです。なんだかぬくもりが感じられます。誰かに優しくしてあげたくなるクリスマスの魅力は、その根っこに神様の愛があるからです。この世界を愛して、独り子イエス・キリストをお与え下さった神様の愛が私たちの心を温めてくれる、ぬくもりの源です。
今治めぐみ幼稚園で迎える初めてのクリスマス、とても楽しみです。そしてみなさまのご家庭に、ぬくもり溢れる愛の溢れるクリスマスが来ますように心よりお祈りしています。
今月の聖書の言葉、「喜ぶ者と共に喜び、泣く者と共に泣きなさい。」は、人の心に寄り添い、感情を共にすることの大切さを伝えています。嬉しい時には共に笑い、悲しい時には共に涙する。そんな「共感力」、「思いやりの心」が大切です。ではその心はどうすれば育つのでしょうか?先ずは愛される喜びの経験をたくさんすることだと思います。自分自身が愛され、喜びを共にしてもらえる人、悲しみを共にしてくれる人と出会う経験、自分の心に寄り添って、ぬくもりを伝えてくれる経験、そんな経験の積み重ねの中で、「共感力」「思いやりの心」が育ちます。そしてこどもたちはもう既にそのような「共感力」、「思いやりの心」を自らの内に持っているんだなと思わされることが多々あります。そのことを喜びながら、こどもたちが幼稚園の生活の中で愛される経験をたくさんしてほしい。なによりも教職員一同、こどもたち一人一人の心に寄り添い、愛を伝える保育の歩みを続けてまいります。今月もどうぞ宜しくお願いします。
さて、子どもたちが、運動会を目指して、楽しく体を動かしている姿、当たり前の姿です。でも、この当たり前の姿の尊さを思います。世界中には、戦争や様々な不正の中で子どもたちが脅かされています。子どもが毎日楽しく遊んでいる風景が当たり前になっていない現実がたくさんあるのです。残念なことです。子どもたちが、生き生きと楽しく遊んで、日々成長の喜びに輝いている。これを尊く思う心、これを決して忘れてはなりません。世の中は、経済優先、力関係が優先されます。しかし、こども達の幸せを尊ぶ心を失ってしまったらいけません。あたかもそれは、塩味を失ってしまった料理のように味わいのない、つまらない社会となってしまいます。そしてこども達の姿を光、希望として常に尊ぶ姿勢が、社会の真の幸せを実現します。
そのような意味からも運動会は、とても大切な行事です。生き生きとした、成長の喜び溢れるこども達の姿を、ご家族の皆様と共に喜び、幸せを実感するひと時とし、実りの秋の素晴らしい思い出としたいと思います。どうぞよろしくお願いします。
さて、夏、8月を過ごしていますと、平和のことを思わずにはいられません。かつての悲惨な戦争の記憶がどんどん風化しているようで心配です。今、憲法改正問題等も話題となっています。ご家庭の皆様におかれましても、政治的には、色々な立場があろうことかも思います。でも、私が幼稚園長として、切に願うことは、幼稚園に通っているこども達が、戦場に行かされたり、戦火に怯えるようなことだけは絶対にあってはならないということです。憎しみ合い、争い合うよりも、愛し合い、支え合う方が良いに決まっています。とてもシンプルなことです。それなのに、世界中で争いが絶えません。痛み、傷つき、飢え、命を奪われている人々が、こどもたちが沢山います。なぜ、それができないのか。本当に悲しいことです。
今月の聖書に、「無垢でまっすぐに見る」姿は、幼稚園のこどもたちにぴったり当てはまる姿です。その姿、その生き方が、平和な人、未来につながるというのです。私たちが素晴らしい未来、平和な未来を創ろうとする時、大切なことは、「無垢でまっすぐな」存在であるこどもたちを常に見ることではないでしょうか。そこから私たちは、平和な未来を創り出す手がかり、エネルギーを与えられるのです。こどものあり方に学ぶこと、とても大切だと思います。こどもは、自ら学び、成長していく存在です。でも私たち大人はが、こどもから学ぶ。そういう姿勢もとても大切だと思います。
二学期、運動会、遠足、バザー、そしてクリスマス。楽しい行事がいっぱいです。素晴らしい成長の喜び溢れる充実した二学期となるように精一杯、保育に励んでまいります。ご家庭の皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
新学期が始まって三ヶ月が過ぎようとしています。ということは私がめぐみ幼稚園に参りましてから、三ヶ月が過ぎようとしていることともなります。こどもたちから「園長先生」と声をかけてもらえることがとても嬉しいです。私も新しい幼稚園でこどもたちを受け入れ、少しでも早く慣れていきたいと一生懸命勤めていますが、こどもたちは私に先んじて、もう既に私を園長として受け入れてくれているのだなあと実感することが多く、本当にありがたいことです。
さて、幼稚園にいる時は、必ずこども達と一緒に給食をいただくことにしています。各クラスを順番に回っていますが、一回りしてまた同じクラスのこどもたちと食事をするまでには結構間が空いてしまいます。そうやって久しぶりに(?)こども達と食事をしていますとずいぶん様子が違うことに驚きます。短い時間の間にこども達は、新しい生活に慣れ、戸惑いを乗り越えて、成長していることを実感し、嬉しく思いました。
そのようにして新しい生活に慣れ、自分自身が安定してくるとこども達は視野が広くなり、新しい遊び、新しい友達、新しい「世界」を「探し」始めます。そして旺盛な好奇心を持って、いろいろな事柄に挑戦していきます。そのような探求活動が旺盛になってくる時期がちょうどこの頃になるのです。そして新しい発見に驚き、新しい関わりの中で、ますます豊かに成長していきます。7月の聖書の言葉は「探しなさい。そうすれば見つかる」です。こどもたち一人一人が好奇心を持って意欲的に探し求める歩みの中で、神様は素晴らしい発見をプレゼントしてくださいます。そうやって「みつかった」ものを共に喜び、成長の糧としながら歩んでいきたいものです。
この時期、そんな「探し求める」こども達の動きに寄り添い、共に探し、見つけたものを共に喜ぶ、その営みの中で、こども達の世界がますます豊かに広がっていくように努めたいと思います。
一学期も残り少なくなりました。安全に留意しつつ、楽しい園生活のために励んでまいります。どうぞよろしくお願いします。
青い空に白い雲、緑の芝生に充実した遊具、「今治にはこんな良いところがあるんだ。」と感心した次第です。美しい自然の中で、お母さんと、お父さんと、ご家族と子どもたちが一緒に遊んでいる様子は、本当に幸せそうで、眩しかったです。本物の幸せは、決してお金で買うことはできないのだなと思わされ、ちょっぴりウルウルしてしまいました。どうも最近、歳のせいか、涙もろくなっていけません。
今回の遠足、家族の幸せの「舞台」となったのは、美しい自然でした。この自然は、神様がお造りになったものです。聖書によれば、神様は、無秩序で混沌とした世界に光をもたらし、海と陸とを分けられ、昼と夜、天体の運行をさだめられました。そして地上に命をもたらされました。青い空、白い雲、輝く太陽、緑の山々、青い海、美しい草花、生き物、全てをお作りなった神様のご感想は「良し」でした。「我ながら良くできた」と満足され、祝福されたのです。
このように世界は、神様がお造りになられたとても良いもの、「傑作」なのです。神様がお造りなられた故に、この世界は、神様のものです。私たち人間は、この世界を、神様が喜ばれるように大切に管理する責任を委ねられているのです。
美しい自然の中で、幸せそうに遊ぶご家族の様子を見ていて、この幸せがいつまでもつづいてほしい。そのためにこの美しい自然、そして平和を大切にしなければならないと改めて思わされました。そして自然の美しさ、尊さ、そこで楽しく遊ぶことのできる喜びを子供たちとともにたくさん経験し、神様に感謝し、大切にする心が育って欲しいと願いつつ保育に励んでまいります。
どうぞ宜しくお願いいたします。
とても良いもの
今年は私も「新入園児」な訳で、少しずつ幼稚園の様子を見て、慣れていこうと務めています。保育の初日、二日目と怪我が続いて、本当に申し訳なく、心配しましたが、その後は大きな怪我もなく過ごしています。こどもたちはのびのびと遊びを楽しんでいます。子供達のありのままの姿を大切に受け止めて、そのこどもこどもに応じた対応を心がけていることがよくわかります。礼拝の時にはしっかりと集中してお話を楽しむことができています。結果として(ここが大切です)とても静かです。賛美歌の音程も正確で、無理して叫ぶように声を出したりしません。自然体で歌っています。とても歌が上手ですね。
前園長を中心として教職員が、キリスト教保育本来のあり方を大切に実践してきたことがよく伝わってきました。キリスト教保育の本来のあり方とは、どういうことかと申しますと、一言で言えば「愛されて愛する者となる」ということができます。こどもたちがありのままの姿を喜びを持って受け入れられて、それぞれの個性に応じた援助を受け、大切に育まれていく。その中で、愛されている喜びを肌で感じ、喜びのうちに成長していく。そのようにして愛されて、大切にされて、育つ中で、他の人のこともたいせつに、愛する者として歩んでいくことができるようになる保育です。
そのような「愛」の根本には、イエス・キリストに示された神の愛があります。神様は愛です。神様はこどもたちが大好きです。「わたしは、あなたたちのことが大好きだよ」という神様の愛のメッセージを、幼稚園の教職員全員で、幼稚園生活のあらゆる営みを通して、こどもたちに伝えて参ります。どうぞよろしくお願いします。
家(牧師館)が耐震改修のため、最低限の家財を運んで堂守室(ガリラヤ館2階)に仮住まいしている。ここは、もうずいぶん前に、幼稚園の主任の野間屋恵子先生、用務・園バス運転手の野間屋大先生が二人で住んでおられた部屋(2DK)だ。幼稚園舎建て替えの際には、臨時の職員室としても用いられたことがある(から、今もその掲示が残っている)。
建物が古くなって、1階の台所こそ別の水道管で飲用水が引かれているが、水は飲めないし、ガスも使えない。3階にある共同風呂・トイレも利用不可だ。いわば、ないない尽くし。ところが、そんなここ(今、その部屋でタイプしている)が、なんとも居心地が良い。どうしてだろうと考えると、思い当たる節がある。
まず、そんな場所を、教会・幼稚園の関係者が、掃除をし、ござを敷き、暖房を用意し、TVの配線をしてくださった。そんな心遣いが暖かい。また、広いスペースがあった頃、夫婦が、別の部屋で、それぞれの用を足すことが普通だったのが、一緒にすることが多くなったので、自ずと新婚時を思い出す(住まいは今の駐車場にかつてあった古い平屋)。
そう、不便な場所に移って、いろいろなものを失ったように思われるのに、かえって、便利な生活の中で、たくさんのものを失っていたことに気づかされる。ふと、思い出す。新潟・妙高の合宿所の狭くて何もない管理別棟で薪ストーブ生活をした時、我が子が見せた生き生きとした顔を。本当に必要なものは、そう多くはないのだ。
ところが、10カ月齢期を境に、例えば、raとlaを識別することが必要でない社会(例えば日本)では、その識別能力が低下する。こう言うと、早期多言語教育を進めているようだが、わたしが注目させられたのは、むしろ、次のことだ。すなわち、「幼児はどうやって言語を習得するか」である。
クールは、シアトルに住む9カ月齢の幼児に中国語を聞かせる実験結果を紹介する。赤ちゃんを数人ずつ4つのグループに分けた上で、第一グループには中国語のネイティヴと本やおもちゃで一緒に遊ばせた。第二グループには中国語を話すビデオを見せた。第三には音声のみ聞かせた。第四は英語を話す人と本やおもちゃで遊ばせた。さて、その結果は?
わたしたちは、第一グループは中国語に反応し、第四は無反応であると確信をもって予測する。そして、第一から第四まで、段階的に反応力が低下すると考えるのではないか。ところが、結果は、第二も第三も、第四と同様無反応だったのだ。そこから見えてくるのは何か。少なくとも赤ちゃんの言語習得には人との交流が「不可欠」だということだ。
今、丹祐月先生がまもなく出産の期を迎える。その後は育休を得られる。育休はほぼ1年だ。この間の、赤ちゃんへの語りかけは大切だ。その際、よく「幼児語」が使われる。クールによれば、言語学習の妨げになると言われることのある「幼児語」も、実は、幼児の学習に役立つのだそうだ。なぜなら、「親子のコミュニケーション」を後押しするからだ。
うかつなことに、子どもたちが絵本と出会う「鈴の部屋」が、なぜ「鈴」の部屋(正式には、<絵本の部屋「鈴」>)なのか、気になりつつも、知らずに来てしまった。お恥ずかしい限りである。前々任の園長のお連れ合いの榎本璋子(あきこ)さんが、今治を去られる前、新園舎竣工直前、に記された文章を最近読んだので、紹介しておきたい。
今治教会機関紙『まぶね』200号(2008年3月)
保育士を始めて3年目になる次男の声には、何か保護者が先生から助言を受けるような響きがあり、ついこの間まで童謡をようやく歌っていた高1の四男の歌声は、山形の山奥の歌に満ちた全寮制の生活の中で、すっかり脱皮して、青年の輝きを感じさせた。彼らも戻って、新学期。子どもたちと目と目を合わせ、声を聴き合う毎日が始まろうとしている。
幼稚園や学校で出会った音階を奏でる楽器は、まずハーモニカで、次にソプラノ・リコーダー、そして、中学生になってアルト・リコーダーだった。リコーダーは、小指の短いわたしには少々苦労なのだが、なぜか気に入ってしまう。
高校時代になると、プラスチック製に飽き足らず、メイプル材や紫檀材のまで買い求めた。また、バッハの『無伴奏バイオリン組曲』のリコーダー用編曲版に挑戦したり、ヘンデルの『水上の音楽』の編曲を吹いて、アンサンブルが奏でる音を想像したりした。
初めてアンサンブルをしたのは大学1年生のとき。グリークラブの4年生の先輩がクラッシック・ギターを弾いて、わたしのリコーダーと合わせてくれた。いつもは、合唱練習をするランキンチャペルの舞台で、うっとり……。「あ、ミス、先輩ごめんなさい。」
今回の練習でも、四分音符を八分音符で吹き急いで「ごめんなさい。」でも、息を合わせ、気配を察して自分のパートを吹き、あるいは一緒に吹くのは、とても楽しい。子どもらのクリスマス・ページェントの中にあるのも、このアンサンブルの喜びなのだと気づく。
園だより
有名なゴスペル「アメイジング・グレイス」の「グレイス」は「恵み」のこと。10月31日は498回目の宗教改革記念日だが、改革者たちは、人間は自分の行いによって救われるのでなく、神の「恩寵(めぐみ)ノミ」によって救われることを告白した。
さて、最近、わたしの出身高校の女子の徽章を手に入れた(男女別)。それは「雪持ち笹」で、緑の五枚の笹の葉の上に真っ白な雪が乗っているもの。女性の清らかさとしなやかさを意味する。男子の方は文武両道を示すペンと矛のデザインで、「雪持ち笹」に敵わない。
ただ、男子(旧制高松中学)の校歌(新制後は校友会の歌)の作曲家の方は、不思議な縁で、島崎藤村詞「椰子の実」の作曲をした大中寅二(霊南坂教会のオルガニスト)だと知る。
その子息の作曲家・大中恩(めぐみ)は、従弟で芥川賞作家・阪田寛夫の詞に曲をつけた童謡「サッちゃん」「おなかのへるうた」で有名だ。同志社小学校校歌も作曲、こちらの作詞は谷川俊太郎だ。♪偉い人になるよりも、良い人間になりたいな、同志社小の私たち。
「要らない新聞紙をください」そう言われて、慌てて新聞紙を探す。切り抜きのために取り除けたものでないことを確かめて、手渡した。すると、もともとそのつもりでなかった束の中のある面に「くせ字の味は人柄の味」という文章を見つけた。書き手は多摩美大卒の井原奈津子さん。18歳から500人以上を収集し、まねて理解を深めているとのこと。
個性的なフォント(書体データ)は売り買いされている時代、個人的に創造するのには限界があるが、「くせ字」ならば無尽蔵だ。そういえば、札幌で北星学園の高校教師をしていた頃、書道教師で書家の山田聳宇(しょうう)先生が、三悪筆と呼ばれた同僚教師の「書」を臨書しながら、その個性を抽出するのを見て驚いたことを思い出す。
めぐみ幼稚園は、自律性を引き出す自由保育をしているが、そういう保育であればあるほど、背後に、伸縮自在ながらも、カリキュラムがしっかりしていなければならないことを意識している。それゆえ、音楽・絵画造形・体育・遊びなどについてまとめてきたが、「きく・はなす・よむ・かく」については、学校化をおそれて、家庭に委ねて来た感が強い。
夏の園内研修では、「きく・はなす」について、絵本・歌・わらべ歌等の実践を意識化・共有化し、3年間を見通すことに手をつけた。「よむ」についても、日常的に文字に親ませていることを確認した。一方、「かく」は未開拓。幼稚園らしく、個々の字固有の造形(リズミックなフォルム)を意識させつつ導入したい。将来の個性豊かな書家(?)のために。
7月園だより
雨の季節はまだつづくけれど
こどもたち全体の集まりの時に、「♪かえるのうたが」を輪唱した。こどもたちが、歌い始めると、先生たちが追いかける。途中、こどもはクヮクヮクヮクヮ、先生はグヮグヮグヮグヮグヮ、こどもケロケロケロケロ、先生ゲロゲロゲロゲロ、クヮクヮクヮ、グヮグヮグヮグヮ。どこまでも追いかけてくるがまがえる、あまがえるたちは逃げる逃げる逃げる。
この題名、実は「かえるのうた」ではなく「かえるの合唱」だ。元歌はドイツ語で、「夏の夜通し、かえるの歌が聞こえる。クヮクヮクヮクヮ、ケケケケケケケケ、クヮクヮクヮ。」わたしは「ケロケロ」と思っていたが日本語でもドイツ語同様「ケケケケ」派が多い。
そんな雨の季節には、6月の賛美歌「♪ぱらぱら落ちる 雨よ雨よ」がぴったりだった。「♪ぱらぱらぱらと なぜ落ちる」。「なぜ?」とふと考える。すると、こう続く。「♪かわいた土をやわらかにして きれいな花を咲かすため」。
雨の季節、きれいな花を咲かすのはあじさい。そして、あじさいにぴったりなのがカタツムリだ。「♪でんでんむしむしカタツムリ お前のあたまはどこにある」。そう! 殻に閉じこもって動かないのが、「角出せ、槍出せ、あたま出せ」に応えて、あたまを出す。
あたまを出しても、まだ見えないものがある。「♪でんでんむしむしカタツムリ お前の目だまはどこにある」。子どもたちが、「角出せ、槍出せ、目だま出せ」と待ちわびていると、じわっと目玉を突き出して、動き出す。そんな姿を子どもたちがクレヨンで写し取る。
6月園だより
♪耳をすまして風を聴く
鯉のぼりの季節が終わろうとしている。風を感じる季節だった。風を受けて気持ちよさそうに泳ぐ鯉のぼりをもう少し観ていたい。子どもの教会では、この季節、凧揚げや紙飛行機飛ばしをする。やはり風を感じるためだ。
風がないと、鯉のぼりも、凧も元気が出ない。実は、人間も同じである。神さまからの風=聖霊(せいれい)を受けて、のびのびとこの世を泳いで行くのだ。その風は強ければいいわけではない。優しく、時には厳しく、愛情のこもった風が人を生かす。
先月も紹介したカトリック神父塩田泉さんの賛美歌集の中に、今時にぴったりの歌「生きる」を見つけて、子どもらと歌っている。余り音程の上下のない楽譜には、「ゆったり委ねて」と指示があって、幼子らにはどうだろうと思っていたが……。
♪耳をすまして風を聴く 神ののぞみを受けとめて
目をこらし風を観る 聖霊のながれ見つめつつ
耳に手を当て「風を聴き」、二本指で向こうを「見つめる」と子どもたちの歌に魂がこもる。
伴奏は、ギターのような沖縄出身の楽器「奏生(カナイ)」だ。以前保護者講演会で来園した「オマチマン」からプレゼントされたもの。小さな指ピックをつけて、一節ごとにCGCG(後半はオクターヴ上)と間奏を入れる。歌とともに子どもたちの心と体も動き出す。
5月園だより
♪キリストの平和が
4月が終わる。こどもたちのあの声も聞けなくなる。「しがつのせいく:しゅイエス・キリストのめぐみとへいわが、あなたがたにあるように。」実は、その聖句に合わせて歌ってきたのが「♪キリストの平和」である。「♪キリストのへいわが、わたしたちのこころのすみずみにまでいきわたりますように」カトリック神父塩田泉さんが学生の頃の作だ。
氏は、その後も、シンプルでやさしい言葉とメロディーの歌を作り続けておられる。昨年以前より在園の方なら、昨年のクリスマス・ページェントの「天使の(マリアへの)お告げ」のところで歌われた賛美歌をご記憶だろうか。あれも、塩田さんのもの。「♪めぐみあふれるマリア、主はあなたとともにおられます 主はあなたをえらび、祝福されました」
さて、「♪キリストの平和」は少々抽象的かなと思い、手話つきで紹介した。「♪キリスト(両掌に釘跡を残す主)の平和(自分の両掌で握手してぐるっと輪を描く)がわたしたちの心の隅々にまで(左手で前を囲んだ内側に右人差し指を上から下へ動かす)ゆきわたります(畳んだ腕を伸ばしながらそろえた指を開いて行く)ように(お祈りの組み手)」
東京町田の「しぜんの国保育園」で保育士3年目の次男・足日(何と読むでしょう?)が、初めて担任となった。3歳児クラスだ。これまで、副担任としてやってきた時とは違って、苦戦している。もっとも、同僚の経験豊かな副担任に助けられているのだが……。
足日は言う。「やっぱり違うね……」、「どこが」とわたし。結局、ベテランは、子どもたち一人一人の性格や、その日園に来た時の様子を踏まえつつ、クラス全体としての動きを予測して、必要な声掛けや、援助をしているらしい。
でも、わたしはひとりごつ。「君も、自作の大紙芝居(オリジナルストーリー)等でがんばってるよ。」つい先日は、「(いわさき)ちひろ美術館」で開催中の「聖コージズキンの誘惑展(スズキコージ絵本原画)」に行って、再び創作意欲を燃やしているようだし……。
「めぐみ幼稚園」も、「ゆうこ先生」「ともこ先生」を送り出し、「ゆづき先生(経験1年)」「ちあき先生(新卒)」「たえ先生(事務室)」を迎える。それぞれ、「めぐみ」の新人だが、個性豊かなスタッフであり、得意を伸ばしつつ成長することを楽しみにしている。
どうか、彼らとベテラン・スタッフで歩み出す、新しい「めぐみ」をよろしくお願いします。これまで通り、子ども・保護者・スタッフが「共に育つ」中で、「やわらかに」「のびやかに」「あわてず」、まだ見ぬストーリーを紡いで行きましょう。はじまり、はじまり。
3月園だより
森永ハイクラウン50年に寄せて
「ロダの会」で絵本や物語を紹介し合う中に、『白鳥とくらした子』(原著1938年)があった。作・絵はシシリー・メアリー・バーカー、『花の妖精』シリーズで有名である。わたしがそれを知っているのは、幼い頃食べた「森永ハイクラウンチョコ」に彼女の『花の妖精』カードが1枚ずつ入っていて、いつも楽しみにしていたからだ。
わたしが卒園を迎えた1964年、普通のアイスクリームが10円、病気の時にようやく30円のアイスを買って貰えた時代に、パッケージも美しく登場した「ハイクラウン」は70円もしていた。なぜこんなぜいたくを……と思われるかもしれないが、実は、父がパチンコのおみやげ(景品)に、家族サービスで、このチョコを選んでくれたのだ(と思っている)。
さて、『白鳥とくらした子』では、女の子の父親が金稼ぎに航海に出る。彼女は留守世話役の家政婦に蔑にされながらも、かつて父が助けた白鳥たちに守られて成長する。何年も経って下船した父は、稼いだ金を人助けで服一枚と交換してしまっていた(実は不思議な服)。そして再会。非を詫びた家政婦は娘の父に赦され、三人は支え合って生きて行く。
父親は、先には、娘のためを思って、結局、娘を置き去りにしてしまった。しかし、今度は、娘のことを顧みずに人助けをして、却って、娘に大切な物を得た。思えば、彼がいない間娘を助けてくれたのも、彼がかつて目の前で苦しんでいるのを助けた白鳥であった。ためにすることはためにならず、ためにしないことがためになる。子育てはこういうもの。
今治キリスト教会の元旦礼拝に、恒例の成人祝福式を行った。時間をつくって4人(10日後にもう一人)の卒園児が来てくれた。その際のプレゼントは、ここの所、エリナー・ファージョン作『マローンおばさん』の小型絵本(絵:エドワード・アーディゾーニ)だ。
ファージョンは、物語の名手、『ムギと王さま』で第1回国際アンデルセン賞を授与されている。そんなファージョンに『エルシー・ドピック、ゆめでなわとびをする』がある。こちらは、シャーロット・ヴォークの水彩画が物語世界を映し出す、大型絵本である。
なわとび上手の少女、エルシーの評判がケーバーン山のフェアリーたちに届く。エルシーは、なわとび師匠アンディ・スパンディから三日月の晩ごとに、なわとびの秘術を教えてもらうことになる。驚くべきエルシー!そして、ケーバーン山はなわとびの聖地に。
やがて、その小さなとびなわが体に合わなくなると、その秘術も出来なくなる。彼女の評判は記憶の底に眠って行く。ここまでが前半。ふと、幼き我が子たちの披露してくれた秘術の数々を思い出す。今は、少々得意だが、普通の青年・少年だ。
物語後半は、ケーバーン山が新しい地主によって開発されようとする危機から始まる。ここで筋を語ってしまうのはNGだろう。ただ、普通のように見える我が子たちの中に、眠っているようだけれどエルシー・ドピックは生きているという読後感のみ記しておこう。
「見よ、兄弟が共に座っている。なんという恵み、なんという喜び」−1月の聖句より 伝道師 松田直樹
私は説教等でよく幼稚園のネタを使わせてもらっているが、その時、「こども」とか「こどもたち」という言葉を使う。説教で名前を出すわけにもいかず、ある種、便利な代名詞として用いているのだ。しかし、「こども」なるこどもがいるだろうか?
実のところ、私にとっても「こども」は「こども」でしかなかった。だが、こどもたちと過ごすうちに、とりわけ、給食を共に食べるなど一緒に過ごすことの多いほし組の「こども」の名前は自然と覚えてくる。最初は似たよう顔に思えて見分けがつかなかった「こどもたち」も、気がつけばどう頑張っても見間違えようがなくなってしまう。そうなれば、自然と、漠然とした「こどもたち」ではすまなくなる。
一月の聖句には共に座っている「兄弟」の姿が描かれている。この「兄弟」になるということは、つまり、そういうことではないだろうか。誰でもいい誰かでも、どうでもいい誰かでもない、その子でなければならないその子として愛する。それも、この「世」に産み落とされて「生きる」と言う同じ運命を背負った兄弟として。
しかし、私たちは祝福された。兄弟と共に座っている今は、その恵みと喜びを祝し、心行くまで遊ぶための時なのだ。神は「兄弟」を祝し、その時を与えて下さった。「こども」と接する時、「こども」と話すとき、「こども」と遊ぶ時、そのような兄弟として接し、兄弟として話し、兄弟として遊ぶことができたら、それは「なんという恵み、なんという喜び」だろうと思う。
12月園だより
クリスマスの香り
クリスマスを待つ季節(待降節=アドヴェント)になると、キリスト教会ではアドヴェントクランツの4本のろうそくに毎週一つずつ点灯して行く。全てのろうそくに灯が点ると、クリスマスは目の前だ。今年も、11月30日のアドヴェント第1日曜に向けて、前日29日に点灯式を行う。併せて、イルミネーションに光が踊る。
わたしが記憶しているアドヴェントクランツは、ヒノキの葉に赤い実の付いたセイヨウヒイラギの葉を加えてドーナツ型に作ったものだ。青い葉が放つ生命の香りが、記憶に残る。今治教会では、クランツと別に、藤田司先生が、毎年、大きなクリスマス・リース作りに工夫を凝らす。時が来ると、先生は香りに包まれつつ、リースを礼拝堂入口に提げる。
嗅覚は、「過去を呼び起こす桁外れの能力を備えている。」「それが何の匂いか、嗅いだときの情景はどうだったのか、その時にどのような感情を覚えたかなどを次々と喚起させる」(樺山紘一編『歴史学事典第2巻』)。ツーンと鼻を突く冷気の匂い、木の葉の香り、そして、燻るろうそくの香り、その全てがクリスマスの到来を告げる。
子どもたちに、自然と暮らしの中にある、様々な香りのプレゼントをしてみては? クリスマス・リースを一緒に作ってみるとか……。きっと、子どもたちの嗅覚を通して、消えることのない思い出が刻まれることだろう。そうそう、本当のヒイラギは、同じ葉形ながら、実の方は紫。ただし、アドヴェントに咲く白い花は、素敵な香りを放つ。
11月園だより
キンダーガートゥナーズ
9月の終わりに、ドイツ・ミュンスターから二人の御嬢さんが今治教会・めぐみ幼稚園を訪れた。東京から福岡まで、(さらに韓国の仁川まで)の自転車旅行の途中で立ち寄ってくれたのだ。四国八十八カ所巡りではないが、教会を宿にしての長旅の一期一会である。
食事を共にしつつ、わたしたち家族は、眼鏡をかけた活発なミリヤと、長い髪の物静かなハンナと会話を楽しんだ。ただ、ミリヤが「何人のキンダーガートゥナーがいるの?」と問うたのに対して、わたしが「110名ほど」と答えると、不可解そうな顔をした。
話の流れで、教諭の数のことかと思い当たったので訂正した。かの語には「幼稚園児;教諭」双方の意味があった。園児の場合が「幼稚園のメンバー」ほどの意味なのに対して、教諭の場合は、語源に即して「子どもの園の園丁(ガーデナー)」である。
ガーデナーは、庭園の造作・維持・管理などの関わり、植物学的知識を持つ専門家。であれば、わたしたち「キンダーガートゥナー」の役割を改めて思う。ただ、その庭は、拘束性の高いフレンチガーデンではなく、より自然なイングリッシュガーデンだろう。
新年度より、国の子ども・子育て支援新制度が始まる。長年目指されていた幼保一元化が、複線(=一体化)の形で実現する。5歳児については、小学校準備教育的側面が強調されるが、むしろキンダーガートゥンならではの教育のひとつの到達点として充実させたい。
10月園だより
「キハ」の疾走
「鉄ちゃん(鉄道ファン)」を自認するチャプレンの松田直樹せんせいは、子どもをわきに抱え、あるいは「お姫様抱っこ」して、砂煙を上げながら園庭を疾走する。ああ、これは「キハ」だ、と思わずひとりごちる。「キハ」とは、鉄道の車両についている記号で、「キ」は制御車(運転台)付きディーゼル車、「ハ」は普通車(イロハの一番下)を示す。
なぜ、「クモロ」、すなわち、制御車付き電車(クモ)のグリーン車(ロ)ではないか。「なおき号」は、どう考えても架線から得た電気でモーター動かし、静かに走る電車ではなく、軽油を飲み込んでガガガーと唸りつつ走るディーゼル車からだ。その乗り心地もグリーン車ではなく普通車だ。でも、子どもたちは、「キハ」を「キイ(特等車)」のように愛す。
実は、昔から「キハ」という呼び名は知っていた。でも、それが何であるかを積極的に調べようと思ったことはない。ところが、以前、教会&園のバザーで手に入れた古本で、小学生向けの絵本『算数と理科の本8 記号のなぞとき』の中の「機関車・電車の記号」の頁を開いたら、出てきた。列車の記号の分類がわかると、とたんに親しみが湧いてきた。
ところで、その際購入した、同シリーズの第17巻最終頁に、これらの本の持ち主であった子どもの字で、「○こんどかう本」「□かった本」「△この本の名まえ」とあった。漢字の使い方から、おそらく小学校低学年。ちゃんと分類して、これらの本を愛読しているのが分かる。今42歳頃の彼(女)は、どんな大人になっているのだろう。
9月園長だより
虫眼とアニ眼
めぐみ幼稚園の先輩教師・白石美恵子先生から文庫本をいただいた。養老孟司・宮崎駿著『虫眼とアニ眼』だ。最初の20頁ほどは宮崎駿の文とカラーのイラストで、いきなり宮崎ワールドとなる。「ぼくの知りあいに 虫眼を持つ少年がいる。絶滅危惧種のメダカだってわけなく 見つけてしまうのだ。ぼくだって子供の頃は持っていたはずなんだが……」
今では子供までも虫眼を失いかけている。そこで宮崎は、「家をかえよう 町をかえよう 子供達に空間と時間を!!」と気炎を上げる。まるで『紅の豚』の主人公「ポルコ」のように。そこで「まず」考えたのは、「町のいちばんいい所に子供達のための保育園(幼稚園もかねる)を!」ということ。園が「まず最初」というのが、何とも、いいではないか。
「子供達が夢中で遊べる所。地域の子供なら、誰でも入れる所。木や土、水と火、いきものと触れる所。子供達が家へ帰りたがらない保育園をつくる!!」「大人が手と口を出さなければ子供達はすぐ元気になる!!」園の地続きにはホスピス、そこに子供達が侵入する。広場は、ただの原っぱ。なんとなくあいている空地。
周りに拡がる町の名は「イーハトーブ」。宮澤賢治の心の中に在る理想郷の名だ。街並みも、家々も造り込みすぎず、それでいて、不思議な調和がとれている。そこには、自由な成長を保証する「設計図」がある。それは、50年前、小さく塀もない幼稚園で、虫や小さな魚を追いかける僕をそのまま受け留めてくれた先生たちの「心」の中にもあったものだ。
7月園長だより
木々のいのち、木々の心を生かして
先日、出来立てほやほやの本が「謹呈」の栞と共に送られてきた。『木霊 百年生きる木造建築』である。その表表紙には、後ろ手に森の木々を見て歩く白い顎鬚を蓄えた紳士、裏表紙は、両手を添えて立派な木を見上げる働き人が写る。帯にはこう書かれている。「こんな大工が、こんな建築家が、とことん議論を闘わしながら、正直な家づくりを続ける…。」
一方、「こんな大工」とは、村尾さんの教え子であり、家づくりのパートナー小川正樹さん。西岡常一の唯一の内弟子で薬師寺西塔の再建に携わった宮大工棟梁・小川三夫から自宅の建築を任されるほどの職人だ。
本の表紙を見た瞬間、教会納骨堂建築の施主として、二人に誘われ、根曲り杉を切り出したばかりの山に、雪を踏みしめ分け入ったことを思い出した。それは、伐採という死の現場でありながら、新しい生への変成の場でもあった。そうなりえたのは、立ち木が、単なる木材になるのではなく、その個性を生かされて新しいいのちの一部となっていくからだ。
わたしたちの子育ても、根曲りの個性的な杉を、扱いやすい建材へと均質化してしまうのでなく、厄介だけれどかけがえのない役を担う素晴らしい柱にしていくものでありたい。それが木々(子どもら)のいのち、その心に応えることだ。
6月園長だより
息子たちを訪ねて
日曜朝礼拝を終えると、東京出張に出かけた。新横浜から横浜線に乗り換え、JR町田駅着、6時間の旅の後、東京在住の3人の息子たちと夕食を共にする。長男が大学生だったころバイトをしていた醤油料理・天忠。味に間違いがないので、安心して会話を楽しんだ。
その夜、次男と三男がシェアするアパート泊。学生の三男は、授業準備が大変だと、奥の部屋へ籠る。保育士の次男も机に着いて、園のバザーに出品するための作品づくりの続きを始めた。小学校の頃手に入れたスズキコージの絵本原画が作業を眺めている。
レースの縁取りが施された段ボール素材の手作りキャンバスには、青空と雲とが配されている。そこに、白い厚紙を立体に組んで、いくつもの雲を浮かばせるらしい。静かに鋏の音が響く。こんなに手間暇かけても、「1,000円くらいで売れたらいいな」とのこと。
月曜は、早朝から満員の小田急電車に揺られ、中央線に乗り換えてお茶の水で降り、夕方まで、キリスト教保育連盟総会と学習会。「子ども・子育て支援新制度」についての講師は新制度の委員とやらで、「まだ公にできないこともある」と歯切れが悪い。
5月園長だより
子どもの日に寄せて
ある休日、田畑の続く郊外に車を走らせた。ソメイヨシノは八重桜に主役を譲り、道々、藤や桐の紫色が目を引く。そんな中、集落のところどころ、五月の節句のこいのぼりが、薫風に泳いでいる。一軒一軒に、家族の愛情を一杯に受けている子どものいることが想像され、心が温かくなった。
節句と言えば、わたしたち夫婦は、道後を訪れると一刀彫「南雲」のお店に立ち寄る。そこに置いてある「桃太郎の誕生」を見るたび手が伸びて、でも、値札を見て、手を引っ込める。もっとも、夫婦のマイブームは、もっと一般的な(安価な!)、しかし、伝統的ないわれを持ち、人情のある「民藝」品の方である。
わたしが一時育った高松には、赤い着衣の「奉公さん」がある。「病を得たお姫様の病を、身に移しうけ、お姫さま全快の祈願をこめて、海のかなたの離れ島に流し人となり、短い一生をおえたおマキ」の記憶を宿す人形だ。以来、奉公人形は子どもの病を身に受けて海に流されつつ、彼らの病を癒してきた。十字架上に人々の罪を引き受けたキリストに似る。
最近、妻が教えてくれたのは、京都・伏見人形の「饅頭喰い」。「両親のどちらが大事かと聞かれた子供が、手に持っていた饅頭をふたつに割り、どちらが美味いかと問い返した」という説話に基づくもので、この人形を飾ると子どもたちが賢く育つらしい。もっとも、飾るのは賢く育てるためでなく、こんな子どもの賢さに目を瞠り、親業を深めていくためなのかも知れない。
4月園長だより
桜の木とともに子どもたちを迎え、送り出し
桜の花がほころび始めた3月の終わり、歴任幼稚園スタッフも大勢迎えて、めぐみ幼稚園の60年をお祝いする会を持った。卒園したばかりの子どもたちの歌に、ここで育った数えきれない子どもたちの面影を追う。98歳となられた第二代園長・上野光隆牧師も、京都から駆けつけて、祝福の祈りをささげてくださった。
集まった人々の中に、一輪、あでやかな、桜色の和服姿があった。30年程前まで主任をつとめてくださった川添先生だ。昨年怪我をされながら、『記念誌(未発行)』のために、園庭で春を彩っていた桜の古木に寄せる一文を届けてくださった。漸く癒えられたら、今度は病で倒れられた。集いへの出席も危ぶまれた。……そして、春。桜は咲いた。
あれは風の冷たい二月ごろの事だったと思います。年長組の子どもたちが桜の太い幹の周りにイーゼルを立ててこの木を描くことになったのです。子どもたちはめいめいその幹にさわって、「固いな」、「どこに花が入っているのかな」などといいながら、鉛筆で描き始めたのでした。春には新しい芽が吹き、やがて蕾が出来てきて花が咲くのだよ、などと口々にいいながら、寒さも忘れて描いていました。……あのころ、桜の古木は画材としては幼児たちには難しいと思ったのですが、出来上がった作品はそれぞれ見事なものでした。子どもたちの真剣なまなざしや、鋭い表現力に圧倒されたことをいまもあざやかに思い出します。そして、あの門の桜が、成長した幼児一人一人の胸の奥にいつまでも残っていると信じています。
川添綾子「刻の宴」より
先日、神谷徹さんがストロー笛で、多彩な演奏をしてくださった。長さの違うストロー、形の違うストロー、それは虫になり、動物になり、ボールになり、ロケットとなり飛んで行った。リコーダーのように指孔を開けて音の高さを変えるものもあれば、トロンボーンのように管の長さを変えて音程を変えるものもある。
先が完全には読めないのがわくわくするリトミックと似て、創り出される音の意外性、時には失敗する(けれどそれを工夫で成功へと導く)手作り感に、聴き手は、聴いているというより、演奏者と一緒になって音を楽しんだ。にんじんトロンボーン作りの実演でも、「ほんとうにうまくいくのかな」……はらはらしながら見守ると……「鳴った!」
どの一つも同じ音色はない。昔読んだ武満徹の言葉を思い出した。「音というのは生命と同じように多様で、たとえばド・レ・ミ・ファ・ソのドの音にしてもフルートの吹く音とオーボエが吹く音とでは性格がぜんぜん違う。……一つの音には測り知れないほどの夾雑物があると考えている。そうじゃないとその音を具体的な音として支えることができない。」
「測り知れないほどの夾雑物」とは、わたしたち人間の「ひみつ」「ふしぎ」だ。兄弟姉妹で、似た遺伝子、似た生活環境を持ちながらも、誰一人同じ子がいないように、それぞれが異なった潜在的可能性を持ち、その子ならではの経験をして成長している。「その子にしか出せない音」を支える「夾雑物」を、美しくも不完全に結晶させながら。
2月 園長だより
鬼はそと!
たまたま新月で始まった新しい年も、満ち欠けする月に導かれながら、新月に戻った。今日は、太陰太陽暦の元旦である。そして、まもなく節分がやってくる。鬼がやってくる……わけではなく、やってくる鬼を払うのだが……。
この季節が巡って来るたびに思い出すのは、息子たちの保育園での節分行事である。時には、「バリン!」、ガラス戸を壊して鬼が侵入してくる(あまりに迫真の演技で、勢いの余り割ってしまったのであるが、観ている方にすれば、ただごとでない)。
ある年の「豆まき」、元気のいい響(長男・ひびき)が、代表して鬼に立ちはだかる。鬼は、「俺たちの国へ行くか?」と問う。響は「いいよ」と答える。するとと、ぐいぐいぐいと本当につれて行かれそうになった。響の顔がこわばる。
やりとりを「ひとごと」として観ていた他の子どもたちも固まる。それを観ていた足日(次男・たるひ)は、固まる域を超えた。不安と怖ろしさにくしゃくしゃとなった顔の奥から、怒りの形相で鬼を睨む。後ずさりしながらも、兄を救おうと、懸命に豆を投げた。
そんな弟を、兄は今も(精神的に)頼りにしている。鬼に勝つだけの力があるからではなく、そんな鬼にでも我を忘れて立ち向かってくれる奴だから。足日は、勤め始めた「しぜんの国保育園(町田市)」で、鬼の役をやると言う。今、その準備に余念がない。
1月 園長だより
かぐや姫の物語
我が家では、子どもたちへのクリスマス・プレゼントに本を一冊買うことにしている。ファッションの世界を目指す三男のために選んだのは『デッサン・ド・モード 美しい人を描く』で、長沢節の書いた本の新装版だった。1917年に生まれ、1999年に既に亡くなっている長沢の、古びることのないデッサンは、彼のことを何も知らないわたしの目を止めた。
ところで、子どものための買い物なのだが、自分の本も一冊買った。和風の装丁が美しい『月のこよみ2014』で、天文関係の出版社から出ているものだ。そこで2014年が月齢0.0から始まる珍しい年であることを発見。この本、毎月の星空も載っていて、天空を黄色い月が満ち欠けしながら、空色の天の川を横切り、赤い軌道を巡っている。
正月4日、上の二人の息子が仕事のため帰京した夜、「月」を題材にした映画『かぐや姫の物語』を家族4人で観た。テーマもさることながら、監督の高畑勲が、極力余計な線を排し、日本の絵巻物の手法を活かして作っているのが、実際どう映るのか気になっていた。果たして、スクリーン上には、まるで紙の手ざわりの画が、生き生きと動いていた。
はっとさせられた。長沢節の服飾デッサンも、『月のこよみ』のデザインも、高畑勲の映像も、こまごまと書き込んだり、べったり塗り込んだりしていない。色も最小限のものに抑えられている。その分、わたしたち見る側の想像力を引き出してくれる。わたしたちの子育ても、そんなものでありたい。8日の今宵は、完全な半月である。虚心に見上げよう。
12月 園長だより
伝えたい・聴き取りたい・感じたい……それだけで
子どもの教会では、11月24日の日曜日、礼拝の後、いつもガリラヤ館の2階で礼拝をしている東洋ローア・キリスト伝道教会と交流した。「手の言葉」を使われる方々とコミュニケーションするということで、予め、指文字での自己紹介や手話賛美の練習をして備えた。
その日、どきどきしながら、会場である牧師室に集まった。しかし、相手方は積極的に手話で話しかけてくださり、こちらもおそるおそる、合っているか合っていないか、自身のない身振り手振りで応じると、気持ちが通い始めた。
そのうち、筆談をも交えながら、とにかく、伝えたい、聴き取りたい、感じたい、ただそれだけだったのだが、気まずい間が生まれる余地もなく、会話が続いていった。そのうち、互いに立ち上がったり、目を大きく見開いたり……ちょっとした祝宴となった。
子どもたちは手話賛美を披露した。その後、何名かが覚えたての指文字自己紹介をしたら、ローアの方々が「こうも表現できる」と、○月ちゃんの「月」は三日月の形とか、藤○ちゃんの「藤」は藤棚から下がる藤の花の形とか教えてくれた。
すると、不思議、ふしぎ、その子の名前が、生き生きと立ち上がった。「手の言葉」が、こうして、存在感豊かに、ぼくたちの目の前に現れた。今度、お会いする時には、習いたての「こんにちは」で、「可愛く」挨拶できると思うと、今からわくわくする。
11月 園長だより
わたしは、「あさ」をテーマとした絵本を二冊持っている。一冊目は、ずっと昔に購入したユリー・シュルヴィッツのDAWN(第5刷1986、初版1974)だ。頁をめくると、山間の湖の、静かなしずかな夜明けに、いつ間にか、入り込む。息子たちにも読み聞かせた。その後、『よあけ』として、瀬田貞二訳(1977)で福音館書店からも出ていることを知る。
10月 園長だより
子どもたちと「お月見」をしましたか?
「9月19日は何の日?」「仲秋の名月」、「お月見をした人?」「見たよ」「……」、「お団子を食べた人」「お団子?」「……」、「ススキを取ってきた人」「……」「……」。実際に子どもに質問したわけではない。でも何人かのお母さんから聞いたところでは、こんな感じだ。
我が家は、その夜、突如思いついて、久しぶりに「お月見」をした。怜の大好きな松田直樹先生も呼んで。妻は有り合わせのうるち米の粉で団子を茹で(餡子も添え)、近くのススキを刈って花瓶に活けた。庭に木のベンチを出して、木の折りたたみ椅子を拡げた。
空は前日ほどクリアでなかったが、満月はそこそこの位置まで上がっている。それを、電線が邪魔をする。街中での月見は無粋だ……としばらく月を眺めていると、やがて、白いまん丸の月は、電線にかかる。今度は、次の電線との間に入る。「ミだ!」「ファだ!」
そうなると、一句ひねり出したくなった。というのも、札幌時代、まだ小さかった息子(2人!)と、住んでいたマンションの中庭から満月を見上げながら、句会でもないが、共に一句をひねり出そうとして、互いの陳腐な句に笑い合ったことを思い出したからだ。
今年の作は、「満月や 空の五線譜かけあがり」。あの日の満月を見上げた次男(保育士)に電話で「どういう光景を詠んだ句かわかる?」と聞いたら、苦笑しながら、一応分かってくれたが、やっぱり陳腐だ。「満月符(=全音符)」に替えると……くどいか……
風流とはとても言えない「お月見」だったが、何かゆっくりした時間が過ごせた。怜と松田先生は、砕石の庭(駐車場)に仲よく這いつくばって、石の間からたくましく生え出たドクダミを臭っている。いつの間にか、満月符は、五線を抜け出て輝いていた。
2学期に向けて、二日にわたって園内研修をした。『実践記録集』のための発表、運動会のイメージ作り、一学期の振り返り、二学期の当面の予定。子どもたちを育てるための課題は山積、難しい顔も、時には涙も。しかし、互いのユーモアの中で笑顔がこぼれる。
だから、というわけでもないが、二日目の最初に、わたしが出したクイズは、蚊とゴキブリと人間、一番速いのは?というものだ。何人かに答えてもらったが正答者はいなかった。ここで、先を読むのをやめて、どれが一番か考えてほしい。答えは最後に記しておく。
ネタ本は、京都の恵文社一乗寺店の書棚で出会った、松田行正編『1000億分の1の太陽系+400万分の1の光速』。太陽系の半径、50天文単位(太陽と地球の距離の50倍=75億?)を1000億分の1のスケール(600頁=7500?=75m)に縮めて表現したものだ。
これを繰っていると、改めて地球と太陽の近さを感じる。また、太陽系で最も遠い海王星でも全太陽系の6割の位置でしかなく、その先4割をなお太陽の作用圏にあることが分かる。ふと、幼いころの子どもとの関わりが、その子の生涯を支える光となることを思う。
編者は、光が1秒間に進む距離30万?を400万分の1にして、同じ頁数の中に表現した。水星を少し過ぎたところに、蚊の飛行速度69?/秒が出てくる。その後、金星さらに地球を過ぎたところに、人間の歩行速度とゴキブリの速度が1.5m/秒で、仲よく登場する。
皆さんは正しく答えられただろうか。わたしたちの想像と、実際とは一致しない。だから、わたしたちの基準で子どもを測るのでなく、子どもが何を思い、どうふるまっているかを注意深く観察して、彼らに寄り添いたい。そこから新たな出会いが始まる。
7月 園長だより
6月 園長だより
5月 園長だより
2013年度4月 園長だより
28年前、今治めぐみ幼稚園でチャプレン=幼稚園付き牧師(の卵)を3年間務めました。その頃、園の正門には大きな桜の木がありました。始園・入園式のころともなると、桜は、幹から広がる枝々を薄桃色の花衣で装って、子どもたちを迎えてくれたものです。
3月 園長だより
2月園長だより
1月 園長だより
12月 園長だより
11月 園長だより
10月園長だより
9月園長だより

夏休みに入った最初の月・火、今治教会の子どもの教会では、休暇村・瀬戸内東予キャンプ場にでかけた(卒園児も多数)。自然の中のキャンプサイトには珍客も現れる。日頃、草や木の枝にくっついて擬態(カモフラージュ)しているナナフシは、テントに張り付いてバレバレ。
7月 園長だより
6月 園長だより
とりわけ、「いのちの息」によって子羊が危機を乗り越える場面は、遠い昔から人々に鮮烈な印象を与えてきた。こうして生き始めた「こひつじ」のいのちがよどまないように、羊飼いである神さまは、その後も、「いのちの息」を吹き込んでくださる。
2012年4月 園長だより
3月 園長だより
2月 園長だより
1月 園長だより
12月 園長だより
11月 園長だより
10月 園長だより
9月 園長だより
8月園長だより
6月園長だより
5月園長だより
2011年4月園長だより